高校を卒業して建設業界で働くことを考えたとき、多くの人が真っ先に気になるのは、やはり「お金」のことかもしれません。「毎月どれくらい給料がもらえるんだろう?」「将来、家族を養えるくらい稼げるようになるのかな?」そんな期待と不安が入り混じった気持ちになるのは、ごく自然なことです。
インターネットで検索すれば、「建設業 高卒 平均年収」といった数字はすぐに見つかるでしょう。しかし、その数字だけを見ても、自分の未来が具体的にどうなるのか、なかなかわかりにくいものです。なぜなら、給与というものは、たった一つの数字で語れるほど単純ではないからです。
同じ「高卒」というスタートラインに立っていても、10年後、20年後には、年収に大きな差が生まれていることも珍しくありません。それは一体なぜなのでしょうか。
大切なのは、平均の数字に一喜一憂することではなく、その数字の裏側にある「給与が決まる仕組み」を正しく理解することです。そして、その仕組みの上で、自分がどう行動すれば着実に収入を上げていけるのか、具体的な「キャリア戦略」を描くことです。あなたのキャリアプランを考えるための、一つのヒントとして読み進めてみてください。
まずは現実を知ろう。データで見る高卒の平均年収と他業種との比較
具体的な話を進める前に、まずは客観的なデータから、建設業で働く高卒者の年収がどのくらいなのかを見てみましょう。国が毎年行っている「賃金構造基本統計調査」という公的な統計データは、こうした実態を知る上でとても参考になります。
この調査によると、建設業で働く高校卒業者の平均年収は、年齢とともに着実に上昇していく傾向が見られます。例えば、経験の浅い10代や20代前半では、他の産業と比べて、それほど高い水準ではないかもしれません。しかし、これはどんな仕事でも同じで、まずは基礎を学ぶ時期だからです。
大切なのはその後の伸びしろです。建設業では、技術を身につけ、経験を積んでいくことで、給与カーブはしっかりと右肩上がりに伸びていきます。特に、現場で責任ある立場を任されるようになる30代、40代とキャリアを重ねていくと、全産業の平均年収を超えるケースも多く見られます。これは、建設業が学歴よりも、専門的な技術や知識、そして現場での経験が正当に評価される「実力主義」の世界であることの表れとも言えるでしょう。
ただし、繰り返しになりますが、これはあくまで「平均」の数字です。あなたの年収がこの平均通りになるとは限りません。大切なのは、この平均値を一つの基準として、ここからどうすれば収入を増やしていけるのかを考えることです。次のセクションでは、なぜ同じ建設業でも年収に差が生まれるのか、その具体的な要因について詳しく見ていきましょう。
同じ高卒でもなぜ差が?給与を左右する「会社規模」「資格」「経験」
年収は、個人の頑張りだけで決まるわけではありません。どのような環境で、どのようなスキルを身につけていくかによって、数年後の収入は大きく変わってきます。特に建設業界では、主に3つの要素が給与に大きく影響すると言われています。
会社の規模と事業内容
一つ目は、所属する会社の規模や、何を得意としているかという点です。例えば、全国各地で大規模なプロジェクトを手がけるゼネコン(総合建設業)と呼ばれる会社と、地域に密着して社会基盤を支える会社とでは、給与の体系や水準が異なる場合があります。どちらが良いというわけではなく、会社の安定性や成長性、そしてどのような仕事に携われるのかといった点が、将来の収入に関わってきます。自分自身がどんな仕事を通して成長したいのかを考え、企業研究をすることが重要です。
国家資格の有無
二つ目は、資格の力です。建設業界には「施工管理技士」といった国家資格があります。これらの資格は、一定以上の実務経験がないと受験することさえできません。資格を取得するということは、国から「専門的な知識と技術を持った人材である」と認められることと同じです。そのため、多くの会社では資格手当が支給されたり、昇進の条件になったりします。資格は、あなたの市場価値を客観的に証明してくれる強力な武器になるのです。
経験と新たなスキルの習得
そして三つ目が、現場で積み重ねた経験と、時代に合わせた新しいスキルです。多くの人をまとめ、現場全体を動かしていく調整能力はもちろん、近年では、BIM/CIM(びむ/しむ)と呼ばれるコンピューター上の3次元モデルで建物を設計・管理する技術など、新しい知識も求められています。経験を土台に、常に学び続ける姿勢が、着実な収入アップへと繋がっていきます。
5年後、10年後の自分は?着実に年収を上げるためのキャリアプラン
年収を上げるためには、目の前の仕事に一生懸命取り組むだけでなく、少し先の未来を見据えた計画、つまり「キャリアプラン」を考えることが大切です。ここでは、入社後のキャリアを3つのステップに分けて、どのように成長していくのかを具体的にイメージしてみましょう。
ステップ1(入社〜5年目):基礎を固め、資格取得を目指す時期
最初の数年間は、とにかく現場で多くのことを吸収する時期です。先輩や上司の指示を正確に理解し、仕事の流れや専門用語を一つひとつ覚えていくことが最優先となります。この時期に大切なのは、わからないことをそのままにしない素直な姿勢です。同時に、将来のために資格の勉強を始めることも重要になります。「2級施工管理技士」といった資格は、実務経験を積みながら取得を目指せるため、日々の仕事と勉強を結びつけることで、知識と技術の両方をバランスよく身につけることができます。この時期の頑張りが、後のキャリアの丈夫な土台となります。
ステップ2(5〜10年目):現場の中心として経験を積む時期
ある程度の経験を積むと、徐々に責任のある仕事を任されるようになります。小さな工事のリーダーを任されたり、新しく入ってきた後輩の指導をしたりする機会も増えるでしょう。この時期には、より難易度の高い「1級施工管理技士」の取得を目指したいところです。自分のことだけでなく、周りの人と協力しながらプロジェクト全体をうまく進めていく力が求められます。多くの困難を乗り越えながら信頼を勝ち得ていくことで、現場に欠かせない存在へと成長していきます。
ステップ3(10年目〜):専門性を高めるか、管理職を目指すか
豊富な経験と資格を手にした先には、大きく分けて二つの道があります。一つは、特定の分野の技術や工法を誰よりも深く極める「スペシャリスト」としての道。もう一つは、複数の現場やチーム全体をまとめ、より大きなプロジェクトを動かしていく「マネジメント」としての道です。どちらの道が自分に合っているか、会社と相談しながらキャリアを選択していくことになります。多くの優良な企業では、社員一人ひとりのキャリアプランを支援するための研修制度や、上司との定期的な面談の機会を設けています。
給与だけじゃない。生涯年収に影響する「福利厚生」という視点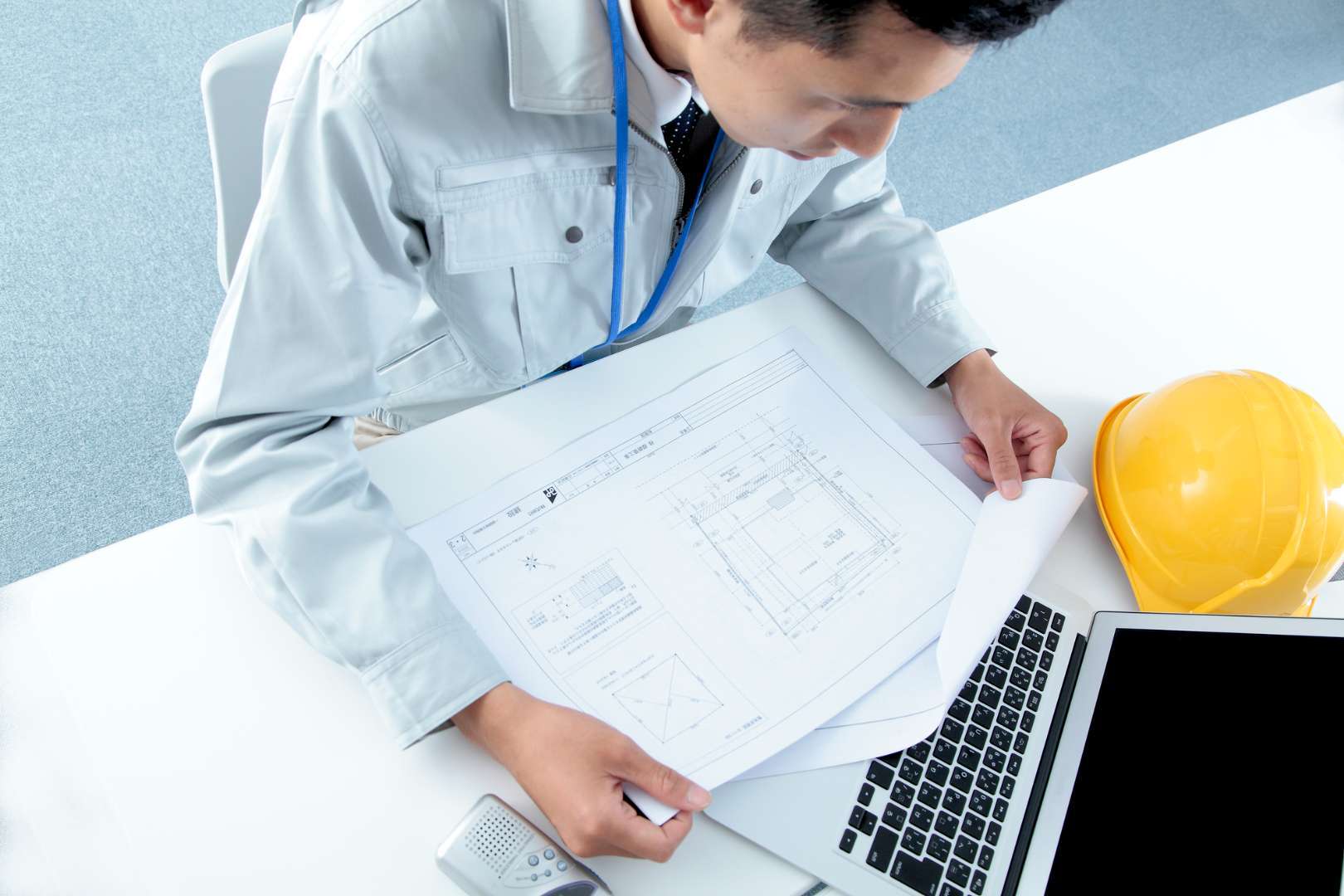
会社選びをするとき、どうしても毎月の給与やボーナスの額に目が行きがちです。もちろんそれも大切ですが、同じくらい重要なのが「福利厚生」です。福利厚生とは、会社が給与以外に提供してくれる様々な支援や制度のことで、これが充実しているかどうかで、実際に手元に残るお金や将来の安心感が大きく変わってきます。
例えば、家賃の一部を会社が負担してくれる「住宅手当」や、安く住める「独身寮」があれば、毎月の生活費をかなり抑えることができます。これは、実質的に給料が上がっているのと同じ効果があると言えるでしょう。給与の額面が少し高くても、家賃を全額自分で払う場合と比べると、年間の手取り額では逆転してしまうケースも少なくありません。
また、結婚したときや子どもが生まれたときに支給されるお祝い金、万が一の病気や怪我で働けなくなったときに生活を支えてくれる保険制度なども、安心して長く働き続けるためには欠かせない要素です。
さらに、将来のことを考えると「退職金制度」の有無も大きなポイントになります。これは、長年勤めた社員に対して、会社が感謝の気持ちを込めて退職時にまとまったお金を支払う仕組みです。目先の給与だけでなく、こうした長期的な視点で会社を見ることが、あなたの生涯にわたる収入を考える上でとても大切になります。信頼できる会社は、社員を大切に考え、その生活を支えようとしてくれます。だからこそ、給与体系だけでなく、福利厚生もしっかりと整えていることが多いのです。
会社の働きやすさや制度についてもっと詳しく知りたい方は、企業のウェブサイトなどで働く環境に関する情報を確認してみるのも良いでしょう。
https://www.maeda-kensetsu.jp/workstyle
結論:建設業は、高卒からでも戦略次第で高年収を目指せる仕事
ここまで、建設業における高卒の年収について、データや仕組み、そしてキャリア戦略という視点から見てきました。平均年収という数字だけを見ると、不安に感じることもあるかもしれません。しかし、大切なのは、その数字はあくまでスタート地点であり、未来は自分自身の行動によって大きく変えていけるということです。
建設業は、学歴に関係なく、確かな技術と経験、そして人からの信頼を積み重ねた人が正当に評価される世界です。資格を取得し、新しいスキルを学び、責任ある仕事に挑戦していく。そうした地道な努力が、着実な年収アップとなって自分に返ってきます。
そのためには、あなた自身の努力はもちろんですが、その努力をしっかりと後押ししてくれる会社を選ぶことが何よりも重要です。社員の成長を支援する研修制度はあるか。資格取得をサポートしてくれる仕組みはあるか。そして、安心して長く働ける福利厚生は整っているか。
これらの情報を会社のウェブサイトで調べたり、説明会で質問したりして、しっかりと見極めること。あなたに合った会社を見つけることができれば、高卒からでも高年収を目指すことは決して夢ではありません。この記事が、あなたの未来を切り拓くための一歩に繋がることを願っています。
何か気になることや質問があれば、気軽に問い合わせてみるのも一つの方法です。


